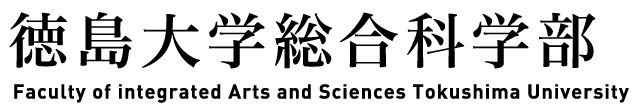徳島大学総合科学部は、文系・理系の垣根を越え、多様な視点から現代社会の課題に挑む研究が進められています。今回はその一例として、私たちの思考や文化の基盤である「言葉」をテーマに、異なるスケールから探求するお二人にお話を伺いました。日本語の「方言」研究を通じて地域社会に貢献する村上先生と、日英韓三か国語の「愛情表現」の比較研究から異文化理解に挑む山田さんです。地域(ローカル)と世界(グローバル)、ふたつの異なる視点から言葉を見つめるお二人の対談から、言語研究の奥深さと、総合科学部での学びの広がりを感じてください。


言葉の世界への出発点
-まず、お二人が現在の言語研究の道に進まれた、それぞれのきっかけについて教えてください。村上先生は、どのような経緯で方言の研究を?
村上先生 私が方言、つまり「地域言語」の研究に惹かれたのは、それが単なる言葉のバリエーションではなく、その土地の歴史や社会、さらにはそこに生きる人々の意識や価値観そのものを映し出す「鏡」だと感じたからです。言葉を深く掘り下げていくと、その背景にある人々の暮らしや文化、社会の移り変わりまでが見えてくる。その繋がりの面白さに気づいたのが、この研究を志した大きなきっかけですね。
-言葉が社会を映す鏡、ということですね。山田さんは、三か国語の愛情表現というテーマに、どのようにして出会ったのですか?
山田さん 私は、国が主催する大学生訪韓団の一員として、韓国に約1週間滞在する機会がありました。そこで現地の文化や歴史に直接触れたことで、もっと韓国語への理解を深めたいという思いが強くなったんです。それがきっかけで、以前から親しんできた日本語や英語とあわせて、三つの言語における愛情表現の違いや共通点に興味を持つようになりました。現在は、ディズニー映画の英語版と、その日本語・韓国語字幕を比較し、それぞれの言語で「愛情」という普遍的な感情がどのように表現されているかを研究しています。

地域から世界へ、 言葉を探求する面白さ
-言葉と社会の繋がり、そこに面白さがあるのですね。村上先生は、具体的にどのようなアプローチでその面白さを探求されているのでしょうか?
村上先生 私は主に二つのアプローチで探求しています。一つは、フィールドワークによって「今、生きている言葉」の動態を捉えることです。対象地域の方々に聞き取り調査を行い、得られたデータを「世代差」や「男女差」といった視点で分析すると、社会の変化が言葉にどう作用しているかが見えてきます。もう一つは、文献資料を遡って、言葉の歴史的な移り変わりを追うアプローチです。こちらは、なぜ今の言葉になったのかという歴史の謎を解き明かすような面白さがありますね。最近では、これらをふまえて中高生の言葉を対象に、価値観の多様化などが彼らの地域言語にどう影響するかを追究しています。
-現在と過去、両方からのアプローチで言葉のダイナミズムを解き明かすのですね。山田さんの研究の面白さは、どのような点にありますか?
山田さん 私の研究では、言語ごとの表現の違いを発見することが特に面白いです。例えば、同じ愛情を示す場面でも、日本語では婉曲的だったり、韓国語では直接的だったり。その違いの背景にある文化や価値観に触れられるのが魅力です。反対に、全く異なる言語なのに似た表現が存在する場面も多く、その共通点を見つけることもまた興味深いですね。言語や文化の違いを学ぶことは、自分で新しい世界への扉を次々と開いていくような感覚。その面白さを実感しながら研究を進めています。
言葉の壁と、その先の発見
-研究を進める上での難しさや、それをどう乗り越えているのかについても伺いたいです。
村上先生 やはり方言調査、フィールドワークにおけるコミュニケーションですね。信頼関係を築き、自然な言葉を引き出すには時間がかかります。また、文献が少ない地域の歴史を紐解くのも地道な作業です。しかし、そうした困難を乗り越えて得られた一次データは、何物にも代えがたい価値を持ちます。苦労して見つけ出した一つの言葉や表現が、その地域の歴史や人々の営みを解き明かす鍵になる。その瞬間の喜びがあるから、研究はやめられません。
-地道な作業の先に大きな発見があるのですね。山田さんは、多言語を扱う上でどのような難しさがありますか?
山田さん 一番は、言葉のニュアンスや使われる場面の正確な理解です。母語ではない英語や韓国語では、辞書的な意味は分かっても、状況による微妙なニュアンスを完全に把握するのは難しい。そこで私は、アメリカや韓国の友人に積極的に質問し、ネイティブの視点から表現の背景にある文化や価値観も含めて学ぶようにしています。友人との会話を通して、辞書だけでは得られない「生きた言葉」に触れることで、理解が格段に深まっていますね。
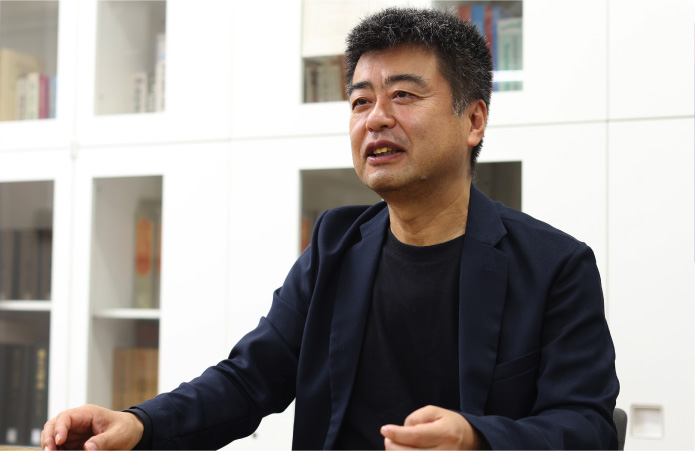
言葉の研究を、社会を支える力に変える
-お二人の研究は、社会と深く繋がっている点も共通しているように感じます。
村上先生 ええ、地域社会への貢献は常に意識しています。その成果の一つが「方言パンフレット」です。元々は東日本大震災の際、被災地に入る医療関係者やボランティアと地元の方々との意思疎通を助けるために作成したものです。現在は、南海トラフ地震に備えて徳島と近隣各地のパンフレット作成にも取り組んでいますが、地域に暮らす日本語を母語としない方々にも役立つよう、多言語対応などの工夫も凝らしています。地域に言語研究の視点からアプローチし、社会に貢献することを目指しています。
-災害時にも役立つ、非常に意義深い取り組みですね。山田さんの研究は、どのように社会貢献に繋がるとお考えですか?
山田さん 愛情という、誰もが持つ普遍的な感情が、文化によってどう表現されるのか。その違いと共通点を理解することは、異なる文化や価値観を持つ人々への理解を深め、共感を育むことに繋がるはずです。そして、その共感が、異文化間の円滑なコミュニケーションを実現する大きな力になると信じています。私の研究が、少しでも多くの人が他文化に興味を持ち、偏見なく向き合うための一助となれば嬉しいです。
分野を越える学び、総合科学部という「よりどころ」
-お二人の研究には、総合科学部の学際的な環境が大きく影響しているようですね。
村上先生 まさにその通りです。地域言語の研究は、その地域の歴史、社会環境、人々の意識などと密接に関わっています。総合科学部には、関連する各分野の先駆的な研究が蓄積されており、それらが私自身の研究はもちろん、ゼミ生の学生の研究にとっても大きな「よりどころ」となっています。ここでは分野の有機的な結合を基盤とした研究が、ごく自然に行われているのです。
-多様な研究が、互いに支えになっているのですね。山田さんはいかがですか?
山田さん 私が異文化に触れながら学びを深めたい、と考えて国際教養コースを選んだのも、総合科学部の柔軟な環境があったからです。また、研究のきっかけとなった韓国への派遣プログラムも、大学の案内で知り、村上先生が背中を押してくださったおかげで参加できました。少し勇気を出して踏み出すことで、想像もしていなかった貴重な経験に繋がったんです。分野にとらわれず幅広い学びに出会え