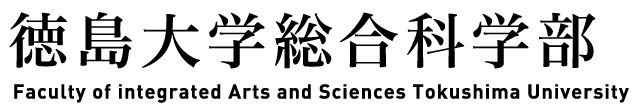徳島大学総合科学部は、文系・理系の垣根を越え、多様な視点から現代社会の課題に挑む研究が進められています。今回はその一例として、「臨床心理学」と「テクノロジー」を融合させ、新しいメンタルヘルス支援の可能性を探る研究室から、指導教員の山本先生と、精神科病院で心理職として勤務する傍ら、博士後期課程でVR技術を用いたメンタルヘルスケアの研究に取り組む山下さんのお二人にお話を伺いました。AIやVRは、私たちの心とどう向き合い、未来のケアをどう変えていくのか?最先端の研究と、それを支える総合科学部での学びの魅力に迫ります。

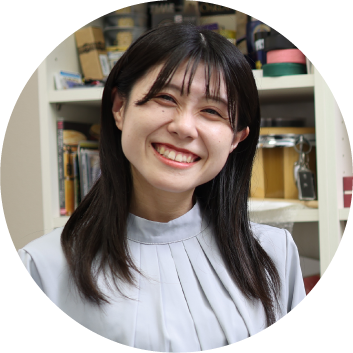
心の世界へ、そしてテクノロジーとの出会い
-まず、お二人が現在の研究分野である「臨床心理学」と「テクノロジー」を活用した研究に関心を持たれた背景について伺います。
山本先生 私は、ヒトの心に関する様々な情報を計測・予測・調整することで、心身の健康増進に貢献する臨床心理学の研究に取り組んでいます。近年は特に、メンタルヘルス支援における専門家不足や地域格差といった課題に対し、AIエージェント(人工知能)を活用することで、新しい支援の形を創り出せるのでは、と考えて研究に注力しています。テクノロジーが、これまで人間が担ってきた役割の一部をサポートできる可能性を感じています。
-AIに可能性を見出されたのですね。山下さんは、臨床心理学への関心と、VR技術との出会いは?
山下さん 臨床心理学には元々強い関心がありました。VR技術という異分野と融合させた研究をしているのは、総合科学部で多分野の知識を統合する大切さを学んだからです。心の問題は非常に複雑なので、多角的な視点が重要だと感じています。VRは時間や場所を選ばず、周囲の目を気にせず利用できる特長があり、支援を必要としていても相談に行けない方々への新しいアプローチになるのでは、と考えました。仮想空間での体験が心に与える影響の大きさにも魅力を感じています。

AIとVRが可能にする、新しい心のケアとは?
-それでは、お二人が開発・研究されている具体的な内容と、AIやVRが持つ「新しい支援」の可能性について教えてください。
山本先生 私が開発しているのは、ユーザーの感情やストレス状態を推定・理解しながら対話するAIエージェントです。日々の感情を「可視化」したり、必要に応じて専門機関へ繋いだり、あるいは対話を通して認知の歪みを修正する手助けをしたりすることを目指しています。この研究の魅力は、人の心に寄り添うことが、テクノロジーの進化で現実的な目標になりつつある点です。生成AIや音声対話、VR/AR技術と組み合わせることで、「共感」や「理解」といった要素も部分的に再現できる可能性が見えてきました。AIエージェントは24時間365日稼働でき、非対面でも心にアプローチできるため、支援の機会を格段に広げられると期待しています。
-AIが常に対話相手になる未来も近いかもしれませんね。山下さんのVR研究では、どのようなケアが可能になるのでしょうか?
山下さん 修士研究では、仮想空間で自分のことを大切に思ってくれている他者の視点を借りて、セルフカウンセリングを行うシステムを開発しました。他者のあたたかい視点から自分の悩みを見つめ直す体験を提供します。現在は博士研究で、多感覚に働きかける、より没入感の高いVRシステムの開発に取り組んでいます。VRの面白いところは、仮想世界での「あたかもそこいるかのような」体験が、現実世界での私たちの考え方や心の状態を変える力を持っている点です。VRを活用すれば、これまで支援が届きにくかった方の心を救う手助けができたり、従来の方法では難しかった全く新しい、効果的なメンタルヘルスケアを生み出せるのではないかと考えています。
研究のリアル “ ワクワクと苦労の先に”
-最先端の研究には、面白さだけでなく難しさもあるかと思います。研究のリアルな側面は?
山本先生 人の心に寄り添う技術が現実になりつつある、そのダイナミズムは大きな魅力です。学生指導では、単に知識を教えるだけでなく、「なぜ研究するのか?(新規性・面白さ)」「社会とどう繋がるのか?(臨床的意義)」という視点を育むことを意識し、学生が主体的に意義を感じながら取り組めるよう、ディスカッションなどを通じて丁寧にサポートしています。
-研究の意義を問い続ける姿勢が大切なのですね。山下さんご自身は、研究のどのような点に苦労し、また面白さを感じていますか?
山下さん 私の研究も、臨床心理学に加え、情報工学や物理学など他分野の知識が多く必要で、それを学び続けるのは大変です。VRシステムの開発自体も、試行錯誤の連続で簡単ではありません。でも、多くの壁を乗り越えた先には言葉にできない感動がありますし、バラバラだった知識が繋がって線になった瞬間の「あっ!」という感覚は、本当にワクワクします。研究は苦労もありますが、やはり楽しい側面が大きいですね。…指導教員である山本先生が、いつもご自身が楽しみながら研究に取り組む姿勢を見せてくださっている影響も大きいと感じています。

「自分にもできる」研究を通じた成長と変化
-研究という経験は、ご自身の考え方にも変化をもたらしたのでは?
山本先生 総合科学部の学生さんは非常に優秀ですが、時にその力を十分に発揮できていない「もったいなさ」を感じることもあります。だからこそ、自分の力を信じて、モチベーションを保ちながら前向きに挑戦できる環境づくり、そして個々の可能性を引き出す関わりが重要だと考えています。
-学生への温かい眼差しを感じます。山下さんご自身は、研究を通してどのような変化がありましたか?
山下さん 一番大きな変化は「こんな自分でも、何か世の中のためにできることがあるのかもしれない」と少し思えるようになったことです。修士研究で開発したシステムを使った実験で、実際に参加者の方々のメンタルヘルスの向上に繋がる結果が出た時の感動は、今でも忘れられません。自分のやってきたことが誰かの役に立つかもしれない、という実感は大きな自信になりました。また、山本先生をはじめ、徳島大学の先生方が、私が自信をなくしている時にかけてくださった、「あなたにしかできない研究がある」「あなたになら絶対にできる」といった励ましの言葉は、本当に大きな支えになりました。正直、以前は何の自信も持てなかった私ですが、自分以上に自分の可能性を信じてくれる存在が周りにいてくれたことで、一歩ずつですが変わることができたと思っています。
分野を越えて、未来を創る 。総合科学部での学びと出会い
-お二人の研究や成長には、総合科学部という学際的な環境が大きく影響しているようですね。
山本先生 そう思います。総合科学部の卒業生は、ここで培った多様な専門性と、物事を多角的に捉える柔軟な思考力を活かして、教育、医療、福祉、IT関連企業など、本当に様々な分野で活躍しています。心理学に関する深い理解と、それぞれの専門分野の知識・スキルを併せ持っている人材は、これからの社会でますます重要になってくると感じています。学際的視点こそが、複雑な現代社会の課題に対して、新しい解決策を生み出せる力を持っていると実感していますね。
-卒業生への期待も大きいですね。山下さんにとって、総合科学部での学びや出会いは、どのような意味を持ちましたか?
山下さん 私の研究テーマ自体、まさに総合科学部で多分野の知識を統合する大切さを学んだことから生まれています。特に複雑な心の問題には、多角的な視点が不可欠です。そして何より、尊敬できる先生方、目標となる先輩、刺激し合える友人との「出会い」が私の財産です。高校時代は勉強が好きでなかった私が、ここで真の学びの楽しさを知り、今の自分がある。先生や仲間との議論、地域での活動、すべてが貴重な経験でした。出会いが人生を変える、総合科学部はそんな場所だと思います。「臨床を通して目の前の人の癒しに貢献し、研究を通してより多くの人々の未来に希望を伝えたい」という、自分が大切にしたい夢もここで見つかりました