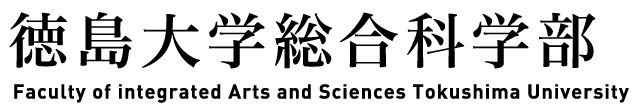アスリートを支える、デジタル時代の自己調整法
徳島大学総合科学部は、文系・理系の垣根を越え、多様な視点から現代社会の課題に挑む研究が進められています。今回はその一例として、多くの人にとって身近な「スポーツ」や「健康」をテーマに、科学的なアプローチで心と身体の可能性を追求するお二人にお話を伺いました。アスリートのパフォーマンス向上から日々の生活まで応用可能な「身心の自己調整法」を研究する中塚先生と、その理論を基に、練習記録をデジタル化する独自のツール「Digital Life Log(以下、DLL)」を開発し、自らの競技力向上にも繋げている藤田さんです。心と身体を「見える化」する、デジタル時代の新しい自己調整法と、その探求を支える総合科学部の魅力に迫ります。

心身健康コース
中塚 健太郎 准教授

心身健康コース4年
藤田 はづき さん
「自分らしさ」と向き合うことから始まった探求
– まず、お二人が現在の研究テーマに関心を持たれた、それぞれのきっかけについて教えてください。
中塚先生 「どうすれば、自分らしく生きられるのか」「緊張や不安とうまく付き合いながら、自分の力を最大限に発揮するにはどうすればいいのか」。私の研究室では、そんな誰もが一度は考える問いに、スポーツ心理学や健康科学の視点からアプローチしています。そのキーワードが「身心の自己調整法」。これは、自分の心や体の状態に気づき、その状態に合わせて自分自身を整える実践的な方法です。この考え方は、アスリートだけでなく、誰もが「自分らしさ」を発揮して生きていく上で、非常に重要だと考え、研究の道に進みました。
– 自分らしく、という普遍的な問いが原点なのですね。藤田さんは、ご自身の経験がきっかけになったと伺いました。
藤田さん はい。私は高校時代から毎日練習記録をつけていたのですが、内容は練習メニューが中心でした。でも、パフォーマンスが良かった時、自分はどんな生活を送り、どんな心理状態だったのか、練習以外のことも含めて記録し、関係性を知りたいとずっと思っていたんです。その後、総合科学部に入学して中塚先生と出会い、自分の心身の状態を客観的に見つめることの重要性や、デジタル記録が持つ可能性について学び、この研究を具体的に進めたいと強く思うようになりました。

データで心と身体を「見える化」する面白さ
– 今回のテーマである「見える化」ですが、お二人の研究では、具体的に何をどのように「見える化」するのでしょうか?
中塚先生 私の研究の核である「身心の自己調整法」は、まず自分の心や体の状態に「気づくこと ( セルフ・モニタリング ) 」から始まります。この「気づき」こそが、いわば「見える化」の第一歩です。そして、その状態に合わせてリラクセーションやアクティベーション(気分を高める方法)などを使い分け、自分自身を最適な状態に「整える(セルフ・コントロール)」へと繋げます。この研究の面白さは、人の心も体も一人ひとり違うので、「正解が一つじゃない」ところ。自分に合った調整スタイルを見つけていくプロセスそのものが、ユニークでワクワクする学びに繋がります。
– 自分だけの調整法を見つけるための「見える化」なのですね。藤田さんが開発されたDLLは、何を「見える化」するツールですか?
藤田さん DLLは、従来の練習記録をスマホやタブレットでデジタル化したものです。練習内容だけでなく、心理状態や生活習慣といった項目も加えることで、心身の状態とパフォーマンスの関係を「見える化」し、自己理解を深めることを目指しています。実際に私自身が活用したところ、自己ベストを更新し続けることができました。さらにDLLは、データを指導者やトレーナーといった、競技者を支えるチーム(アントラージュ)とリアルタイムで共有できるのが大きな特長です。これにより、選手の状態をチーム全体で可視化でき、従来の記録以上に心身への理解が深まり、より的確なサポートが可能になることが分かってきました。
科学的サポートが、試行錯誤を成長に変える
– 中塚先生は、学生が研究を進める上で、どのようなサポートを心がけていますか?
中塚先生 大学での学びは、ただ知識を覚えるだけではありません。総合科学部には様々な専門領域があるので、それらを活用しながら「自分で考え、選び、行動できる」人材を目指してほしい。ですから、教員から答えをもらうのではなく、教員をパートナーとして、共に解決策を探る『学び合い』を経験してほしいと思っています。
– 教員は答えをくれる人ではなく、共に探すパートナーなのですね。藤田さんは、DLLの開発や研究を通して、どのように成長できましたか?
藤田さん DLLを自分で活用することで、心身の状態とパフォーマンスの関係が客観的に見え、自己理解が格段に深まりました。さらに、先生からフィードバックをいただく中で、体重や疲労、心理状態といった多様な情報が、自分のパフォーマンスにどう結びついているのかを客観的に分析できるようになり、視野が大きく広がりましたね。この研究を通して、科学的なデータに基づいて自分を分析し、改善していくというプロセスを実践できたことは、競技者としても研究者としても、大きな成長に繋がったと感じています。

「自律」と「持続可能性」が拓くアスリート支援の未来
– お二人の研究は、これからのアスリート支援をどう変えていく可能性があるのでしょうか?
中塚先生 自分で心身の状態を整える「自己調整」の力を育てることは、これからの多様な社会や、専門家が不足しがちな地域社会でのWell-being(心と体の健康)を支えるカギになります。この考え方は、スポーツだけでなく、教育や福祉、ビジネスなど、あらゆる分野で「自分らしく、力を発揮する」ための基盤として活用が期待されています。
– アスリート支援に留まらない、社会的な意義があるのですね。藤田さんのDLLは、どのような未来に繋がりますか?
藤田さん DLLの活用が進むことで、選手自身が自分のことを考え、行動できる「自律型アスリート」の育成が期待できます。さらに、指導者不足や、指導者が遠隔地にいる場合でも、DLLを通して選手のことを効率的かつ的確に把握できるようになります。これによって、より柔軟で持続可能な競技者支援体制を構築できると考えています。将来的には、この研究で得た経験を活かし、地方におけるアスリート支援の新しい方法や、指導体制の整備にも貢献していきたいです。
挑戦を歓迎する、総合科学部という学びの場
– 最後に、総合科学部が持つ魅力について教えてください。
中塚先生 ここは、ただ知識を覚えるだけの場所ではありません。「なぜできないか」を問うのではなく、「どうすればできるか」を仲間と共に探求する。そんなワクワクする学びが「楽しい」と感じられる時間と空間が、総合科学部にはあります。
– 藤田さんにとって、総合科学部はどのような場所でしたか?
藤田さん 総合科学部は、私の「やってみたい」という想いを、挑戦、そして結果へと導いてくれる場所でした。そのための科学的なサポート体制が、ここには整っています。そのおかげで、多様な学問分野に触れて物事を多角的に捉え、自分のパフォーマンス向上という視点だけでなく、「地域」や「社会」へと視野を広げることができました。素晴らしい出会いにも恵まれ、日々成長を実感できたこの環境が、私は本当に大好きです。
– 中塚先生、藤田さん、本日はありがとうございました。スポーツ心理学に基づく「自己調整」という考え方と、それを実践・共有するためのデジタルツール「DLL」科学的な理論と具体的なテクノロジーが結びつくことで、アスリート一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、持続可能な支援の未来を創り出そうとしている様子が伝わってきました。そして、その挑戦が、学生の「やってみたい」という想いを尊重し、多角的にサポートする総合科学部の環境で花開いていることも印象的でした。最後に、お二人から高校生へのメッセージです。
中塚先生 「できる理由」を一緒に見つけよう!そんな大学生活を、徳島大学総合科学部で一緒に始めてみませんか?
藤田さん これから未来を切り開いていく皆さん、勇気をもって一歩踏み出し、総合科学部での新たな発見や課題への挑戦を楽しんでください!